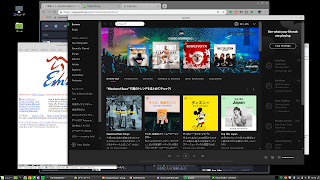Linuxでの省電力設定

先日,バッテリーを交換したThinkPad X1 Carbon, 基本バッテリーで運用 バッテリーが減ったら充電 という,スマホと同じような運用をしばらくしていたのですが,やはり,これはこれでバッテリーの充電サイクルが増えるのが気になる。また,バッテリーを100%まで充電することそのものがよくなくて,80%程度までの充電にしておくと,寿命が劇的に伸びるらしい。 結局、ノートパソコンは電源につなぎっぱなしにして良いの?ダメなの? [lifehacker] 確かに,メーカー製PCだと,満充電させないためのユーティリティがついていることもある。が,実はこのPCはLinux (Linux Mint)を入れて使っているので,Lenovo純正のユーティリティは使えない。 で,調べてみたところ,Linux上でもtlpというソフトを使うことで,自動的に省電力設定を有効にしたり,バッテリーの充電閾値を設定したりできるようなので,インストールしてみた。また,現在の消費電力を確認することができるpowertopというソフトも入れてみた。 powertopはコマンドラインのソフトで,こんな感じ。 で,tlpをインストールし,/etc/tlp.confで, START_CHARGE_THRESH_BAT0=75 STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80 と設定すると,バッテリー残量75%で充電開始し,80%でストップするよう。 また,デフォルトの設定で,バッテリー使用時の消費電力を劇的に減らしてくれる。 とりあえず,これでしばらく使ってみようかな。